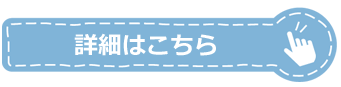新年を迎えると、神様によい1年をお祈りしたり、おみくじなどの占いを行ったりしますよね。おせちを食べたり、凧揚げをしたり、初詣にいったりと楽しい行事がいっぱいです。しかし、三が日だけがお正月ではありませんよ!ここでは、お正月には欠かせない開運行事である「鏡開き」について紹介していきます。
鏡開きとは
正月行事のひとつで、お供えしてあった鏡餅を下して、雑煮や汁粉に入れて食べるお祝いのことです。1月11日に行われることが多く、開運の行事としても有名です。
鏡餅とは
そもそもお供えする餅を、なぜ鏡餅と呼ぶのでしょうか。それは、ご神体の文化と、丸い形に理由があります。古来より、丸いものには神が宿ると考えられ、ご神前にはご神体としても鏡が祀られていました。鏡餅の形のルーツはここにあります。また、お餅は古くから、捧げものとして用いられ、歳神様のご神体でもあると考えられていたのです。そのため、丸いお餅である鏡餅は、縁起物としてご神前に捧げるために、お正月に必要不可欠な存在になりました。
鏡餅から霊力をいただく
お正月に捧げた鏡餅には、歳神様の霊力が宿ると言われています。松の内が終わり、神様がお帰りになってから、その霊力をいただきます。これによって、新たな生命力をいただき、健康な一年を送ることができるとされています。
ご縁をつなぐ言葉選び
実際の鏡開きでは、鏡餅を金づちなどを使って、砕きます。しかしながら、鏡砕きとか、鏡割りなどという言い方をせず、「開く」という言葉を選んでいるのです。これは、神様が宿ったお餅を開くという縁起のいい表現を使うことで、ご縁を絶やさないようにという願いが込められているからだと言われています。
歴史的な行事としても楽しんで
お正月は、家族や友人とゆっくり話ができたり、お酒をいただいたり、一年の運勢を占ったりと楽しいことがたくさんあります。鏡開きを含め、色々な正月行事には歴史的な意味があるので、その意味を考えながら行事を楽しんでいけると、更にお正月を満喫できますね。
当たる電話占いランキング【2024年最新版】